
|

ドロップハンドルSTI仕様に改造を施したブリヂストン アンカー XCS9F
【拡】ドロップハンドルSTI仕様に改造を施したブリヂストン アンカー XCS9F
その名の通り、MTBにドロップハンドルを付けてしまおうという計画。何故わざわざロードレーサーではなくMTBにドロップハンドルを付けるのかというと、ロードレーサーは交通手段としては悪路に弱すぎ、街中の縁石など細かい段差が多い環境には不向きである。また、雨天ではブレーキがまったく効かず、溝のないスリックタイヤは滑りまくりで、とてもではないが街中を飛ばすのに適したバイクではない。
本計画のドロップハンドルMTBは交通手段として街中を走ることを主に想定したものであり、700cのロードより26インチのMTBの方が小回りが利いて都合がよく、ロード用のキャリパーブレーキより格段に強力なディスクブレーキは雨天でも制動力が落ちにくく一般道に向いている。だからこそMTBにドロップハンドルというワケだ。
●メリット
ドロップハンドル採用により自由なポジションが得られ、長距離でも疲れにくい。
幅の細いオンロードタイヤは舗装道路で高速走行に適する。
MTB用のフレームとFフォーク、小径26インチホイールは剛性が高く段差に強い。
26インチホイールは小回りが利きく。
ディスクブレーキはストッピングパワーが強大で、雨天走行時でも制動力が落ちにくい。
700cより小径なホイールは低重心なため低中速域で安定感がある。
デフォルトのMTBに比べ軽量。
抜群のオリジナリティ。
●デメリット
デフォルトのMTBと比べると悪路走行に弱い。
ロードレーサーに比べると重量がある。
ロードレーサーに比べると高速巡航が不利。
ディメンションの関係でステムが短くハンドルのクイック感が強い。
■換装パーツ
■フロントフォーク
■ディレイラー
■ハンドル回り
■補助ブレーキ
■クランク
■ブレーキ
■その他のパーツ
■マーキング等
本計画はMTBを完璧にスマートなオンロード用ドロップハンドルSTI仕様にするという前提でMTBを購入しているので、他サイトで紹介しているツーリング仕様や突発的なMTBドロップハンドル換装計画とは一線を画する内容となっている点に注目してほしい。無駄に資金を投入しています。(^^;
■換装パーツ
当初は型遅れでお買い得感のある9速のDURA-ACEを付けるつもりだったが、ネットオークションでニューULTEGRAをコンポで衝動落札してしまったのでこれをメインコンポに当てることにした。
MTBにロードパーツというのはクールでカッコイイと思う。詳細な換装パーツは以下の表の通り。
 バーテープは白に変更しました。
【拡】バーテープは白に変更しました。
|
| 品 名 |
デフォルト仕様(換装前) |
ドロップハンドルSTI仕様(換装後) |
重量(実測) |
費用 |
| フレーム |
ブリヂストン アンカー XCS9F 440mm |
同 左 |
1,510 |
73,500 |
| ヘッドパーツ |
FSA NO.11G |
同 左 |
87 |
| 前フォーク |
ROCH SHOXS JUDY XC |
テスタッチ ディスクリジッドフォーク |
950 |
15,120 |
| ハンドルバー |
カロイ AL001 560W* |
日東 NeatM.153 STI(400mm) |
290 |
2,350 |
| ステム |
アンカーオリジナル スーパーライトアルミ |
日東 UI-5GX SPECIAL(70mm) |
167 |
4,000 |
| アンカーキャップ |
スターナット |
ヒラメ マルチプレッシャー・プラグ |
39 |
1,710 |
| グリップ |
ベロ VLG309AD2* |
コルクバーテープ |
51 |
790 |
| リヤディレーラー |
シマノ Deore RD-M510SGS* |
シマノ ULTEGRA RD-6600SS |
209 |
5,048 |
| Fディレイラー |
シマノ Deore FD-M510φ31.8 バンド式 |
← |
128 |
|
| STIレバー |
シマノ Deore BL-M510* |
シマノ ULTEGRA ST-6600 |
490 |
21,857 |
| ブレーキ |
シマノ BR-M495 ディスクブレーキ |
AVID BALL BEARING ROAD(×2) |
406 |
18,300 |
| ブレーキローター |
シマノ SM-RT51 |
← |
320 |
|
| 補助ブレーキレバー |
|
テスタッチ エイドアーム |
87 |
2,047 |
| チェーンホイール |
アンカーオリジナル 44-32-22T 170L |
シマノ DURA-ACE FC-7701 52-39T 170mm |
594 |
14,000 |
| ボトムブラケット |
シマノ BB-UN25 110L 68W |
シマノ DURA-ACE BB-7703 68W |
219 |
4,200 |
| スプロケット |
シマノ CS-HG50 11-32T 9S* |
シマノ ULTEGRA CS-6600 12-25T 10s |
235 |
4,400 |
| チェーン |
シマノ CN-HG53 106L* |
シマノ ULTEGRA CN-6600 |
280 |
1,876 |
| Fハブ |
シマノ HB-M495 ディスクハブ 32H |
シマノ DEORE LX HB-M585 32H |
201 |
15,290 |
| Rハブ |
シマノ FH-M495 ディスクハブ 32H |
シマノ DEORE LX FH-M585 32H |
389 |
| クイックレリーズ |
|
シマノ DEORE LX 前後 |
149 |
| リム |
アレックス DP20 32H ディスク専用 |
アンブロシオ バラックXC 32H |
1100 |
| スポーク |
#14 ステンレス |
DT 2.0 Black |
380 |
| タイヤ |
IRC シラクXC ライト 1.95* |
パナレーサー T-Servレーシング 1.25(×2) |
460 |
5,770 |
| タイヤチューブ |
* |
1.0〜1.25 |
210 |
700 |
| サドル |
アンカーオリジナル レーシング クロモリレール |
セラ-サンマルコ 2004 ERA K Ti ホワイト |
225 |
7,970 |
| シートポスト |
カロイ SP369 φ27.2×300L |
シマノ ULTEGRA SP-6600 φ27.2×270L |
214 |
3,700 |
| シートピン |
φ31.8 バンドクイック式 |
BAZOOKA カーボン アーレンキータイプ |
30 |
441 |
| ペダル |
アルミ フラットタイプ VP-320 |
シマノ PD-M520S |
380 |
3,110 |
| 9,927 |
206,179 |
| サイクルメーター |
|
キャットアイ CC-MT300 |
36 |
1,890 |
| フレームポンプ |
|
blackburn Air Stik AS-1 |
148 |
3,100 |
| ボトルケージ |
|
ミノウラ AB100-4.5/ |
36 |
610 |
| ユニコ PET ケージ |
50 |
504 |
| ライト(フロント) |
|
キャットアイ HL-EL120 |
90 |
1,350 |
| ライト(リア) |
|
キャットアイ TL-LD250R |
50 |
1,160 |
| リフレクター |
|
キャットアイ RR-160-BS3R |
|
105 |
| サドルバッグ |
|
ハクバ写真産業 PixGEAR |
|
980 |
| 410 |
9,699 |
換装して余った安物以外のパーツ*はRAFD-421改に転装してリサイクル。
■換装作業開始!
□完成車をバラす
どんどんバラしていきます。分解するのは楽しい。(^^
スタンドはタキザワの通販で購入したものだが、安価(880円)な割に安定性があって車輪も回せるので整備がすごく快適になった。これは便利!

↑このスタンドはもっと早く買っとくべきだった。他店では1,800円程度で販売。
まずはフレームにFフォークを取り付ける。フォークは当初ROCK SHOXのJUDY XC をそのまま使うつもりだったが、バラしてみてJUDY XC単体のあまりの重量に気付いて換装することにした。重すぎ。

2kg以上の重量。フレームより重い… 肩下は約430mm。
サスペンションフォークは重くてメンテナンスも面倒。それに別にサスペンションを必要としているワケでもないのでリジッドフォークにすることに決めた。カーボンとチタンは価格面で断念。アルミは衝撃吸収性の点でイマイチ。で、クロモリ製にしたのだが、ストレートフォークははやり衝撃がモロにハンドルにきそうなのでベント形状のテスタッチのディスクリジッドフォーク(約1,090g)を選択。思っていた以上にいいデザインをしており気に入った。コラムをカットすれば950gくらいになるだろう。
ロードの主流であるカーボンフォークと比べると倍くらいの重量だが、その分頑丈なのでロードとは比べものにならないくらいハードな走りが可能だ。MTBドロップハンドル化の真骨頂。

見た目をスマートにするためコラムはできるだけ短くカットする。

テスタッチのFフォークはベストチョイスと思う。
テスタッチのFフォークは肩下が405mmでヘッド部が25mmほど低くなり高かったハンドル位置を低く設定できて具合がよい。カラーが色々選べるのもいい。
ロゴがないと無印良品っぽくて安そうなので、イーストンのマーキングを施す。高級感が出ました。(笑
リアは問題なく10速のULTEGRAに換装。フロントディレイラーもロード用の105を調達したが、なんと思わぬ落とし穴が待っていた。ロード用…というか、ダウンスイングのタイプだとシートチューブのボトルケージのネジ穴に干渉してしまいボトルケージが装着できないという事態に。
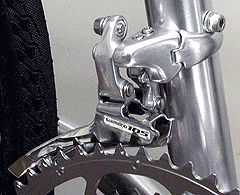
ダウンスイングタイプはボトルケージのネジ穴に当たり使えない。
ボトルケージは絶対使いたいのでMTB用のトップスイングタイプのXTあたりのものに買い直すことを考えたが、XTのFディレイラーの対応アウターは44T。53Tのアウターには無理がありそうなので48Tに対応しているデフォルト装備のDeore FD-M510をそのまま使うことにした。ホントはもうちょっとグレードの高いパーツを使いたいところなのだが…。ということで、コチラのパーツも「Deore」のロゴを消して「DURA-ACE」ロゴをマーキング。
【拡】あれ、トップスイングタイプのDURA-ACEなんてあったの? なんちゃって。
メーカーが保証する「Deore」の対応アウターギアは48Tだけども、調整をちゃんとすれば53Tでも問題なく変速する。もっとも、このFディレイラーとチェーンホイール(53-39)の組み合わせだと変速性能が若干落ちるので参考にする人は自己責任で。(結局別の理由でアウターを52Tに換えちゃったけど。)
ST-6600とFD-M510の組み合わせは、ストローク量が違うので変速性能は落ちるが、変速に問題はない。
ワイヤーの微調整にはアジャスターを用いるのだが、MTBにはダウンチューブにシフトレバー台座がないのでSTIのアウターストッパー(アジャスター)を取り付けることができない。もっともリアディレイラーは本体のアジャスターで事足りるのでなくても支障はない。

本来フレームに取り付けるアウターストッパー。
一方、フロントディレイラーの方はそうはいかないので別途考える必要があり、思案した結果後記するAVIDのディスクブレーキに同梱されていたアジャスターを活用することにした。スマートかつリーズナブルに問題をクリア。

【拡】AVIDのアジャスターを流用。
【参考】TNiから「ロケットアジャスター」「ミニインラインアジャスター」という同機能を果たす製品もリリースされている。
MTBはハンドルが一文字のフラットバーのためロードに比べトップチューブが30〜40mm長い。であるからロード用のドロップハンドルを付けるとさらにサドルとハンドルの位置が遠くなってしまう。そんなワケでステムの短縮化とリーチ(突き出し)の短いドロップハンドルをチョイスする必要がある。
幸いなことにブリヂストンの「XCS9F(440mm)」はトップチューブが535mm(水平556mm)と他のMTBより15〜30mmほど短いのでドロップハンドル化に向いている。特に外車は腕の長い欧米人向けにトップチューブが長くなる傾向にあるようだからやはり国産フレームがベターといえるだろう。
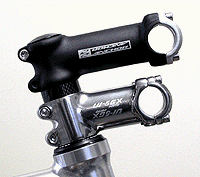
ステムはデフォルトが100mm(上)だったが、30mm短い日東のUI-5GX(70mm)をチョイス。

ハンドルバーは日東のNeat M.153 STI(400mm)をチョイス。
リーチは80mmでごく一般的なものより若干短い。
さらに短いNeat M.104(リーチ:65mm)というものもある。
「Neat M.153 STI」はシマノのSTIレバーに合うように設計されたハンドルバーなので、STIレバーを取り付けたときのフォルムは絶美である。
<追記>
ステム70mm+リーチ80mmの組み合わせでも遠い感じだったので後日換装した。→第二次換装軽量化計画
最初は付ける気はなかったのだが、ちんたら走行時に気軽にプレーキングができ、体重を後方に移してダウンヒル的なMTB本来の乗り方もあるかと思うので取り付けることにした。取り回しも結構スマートだったというのも理由のひとつだが。製品は色々なメーカーから出ているが、テスタッチ製が一番いい感じ。

TEATACHのエイドアーム。目立たないようにブラックカラーをチョイス。


【拡】ハンドルバーへの取付はこんな感じ。
品質自体は値段相応でかなりチープ感があり剛性的な信頼感は薄い。レバーの引きの方は引き城が少なくかなりピーキーなので一気にロックするなんてこともあり、コーナーリング中などの微妙なブレーキング操作が必要な場面ではまず使い物にならない。直線や低速域での使用に限定するべきだろう。しかし、リラックスポジションでのブレーキングが気軽に行え、使い慣れるとかなり便利なパーツだ。
フロントブレーキはレバーとブレーキキャリパー双方が左側に付いているのでワイヤーの取り回しがキツく、これを解決するためにヒラメのバナナを使用した。
◎補助ブレーキレバーの取り付けは「サイクルベース あさひ」が参考になります。
オンロード仕様ということで、MTB用のクランク・アウターリング44Tは小さすぎるのでロード用に換装。最近のMTB用の4本アームはどうみても格好悪いという理由も大きいですが。ギアはトリプルもいらないのでギアチェンジトラブルの少ないダブルにする。
しかし、クランクには苦労した。MTBは太いタイヤの装着が前提なのでチェーンステーが両側に大きく張り出している。その結果、ロード用のクランクとBBをそのまま装着するとチェーンリングとチェーンステーが干渉してしまい使えないのだ。せっかく購入したニューULTEGRAが無駄になってしまった…。
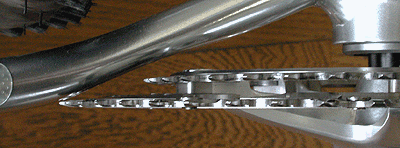
ダブルのDURA-ACE FC-7701を取り付けたところ。
チェーンリング(52T)とチェーンステーがぶつかってしまいまったく使えない。
対応策としてトリプルのDURA-ACEを新たに購入してみた。自転車の顔ともいうべきチェーンホイールはいいものを使いたい。ホローテックIIの7800系ニューDURA-ACEはデザインが好みではないので敢えて7700系をチョイス。(もっとも現時点では7800系のトリプルはまだ発売されてませんけど。)チェーンリング(53T)とステーとの間隔は約1.5mm程度でギリギリだが、なんとかOK?
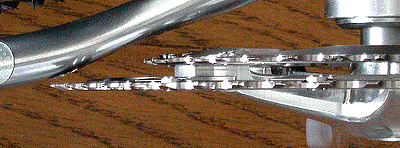
トリプルのDURA-ACE FC-7703+BB-7703を装着。
チェーンリング(53T)とステーの間隔は約1.5mm程度でギリギリ。
試走してみた結果、やはり1.5mm程度の間隔だとダンシングを行うとフレームがたわんでチェーンリングとチェーンステーが接触してキズついてしまった。

キズつきました。(T_T シルバー塗装のアルミフレームだから目立たないのがせめてもの救い。
さらにクランクとBBがなじんできてボルトの増し締めでアウターとステーの距離がほとんど0mmに。このままだとステーが更に削れて強度的にまずそうなのでチェーンリングを53Tから直径の小さい52Tに換装。間隔は2mmほどに広がり接触の心配はなくなった。

FC-7800の52T。オリジナリティはさらに高まったが…。
最近はずっとトゥクリップ付きのペダルを使っていたが、近頃はSPD対応シューズのデザインが街ではいても違和感ないくらいマシになってきたのでビンディングペダルに回帰してみる。SPDシューズは実に歩きやすい。
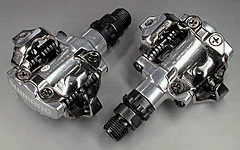
シンプルデザインでコストパフォーマンスの高いPD-M520をチョイス。
やはりビンディングタイプはパワーロスがなくてタイム的に4%は短縮できる。
デフォルトでは1.95のオフロードタイヤが付いていたが、オンロード専用マシンなのでオンロード用の細いタイヤ1.25に換装。タイヤが細いと気分的にも軽くなった感じがしてよい。ただ、衝撃吸収性が落ちることにはなるが。

グリップ力が高く軽量のパナレーサーT-Servレーシング。
1.25と1.95の比較。かなり印象が違ってきます。重量は1本450gから230gと約半減。

【拡】1.25と1.95の比較。
本計画の最大の難関であるブレーキ廻り。デフォルトのブレーキ・シマノ BR-M495は、ロード用STIではレバー比の違いからディスクブレーキがうまく働かない。普通にセッティングした場合、レバーを目一杯引いてもブレーキパッドがディスクローターに届かず、逆にシビアに調整するとちょっとレバーを引いただけですぐロックしてしまい大変危険なのだ。
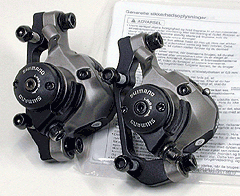
デフォルトのシマノ BR-M495 ディスクブレーキ。
□ロード用STIでディスクブレーキを使う
そのままではどうしても無理なのでストローク量を変更するアダプターを噛ませてやらなくてはならない。素直にカンチブレーキにすれば何の問題もないのだが、このフレームのリアにはカンチの台座がないのだよ。もうやるしかないのだ。
アダプターを自作することも考えたが、ブレーキは命に関わる重要なパーツなので強度的に不安を拭えない自作はやっぱりやめた。結果、STI・ERGOレバーでメカニカルディスクを使用できるという『TravelAgent(In-Line)』の購入も考えたのだが、物の割に高価(1ヶ:3,500円〜)で見た目も無骨でクールではなく、バイク全体のスマートな雰囲気を台無しにしてしまうので却下。
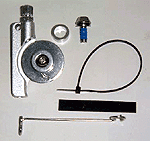
【拡】これがそのパーツ。実用一点張りでデザインや質感は最低。
ちなみに、Vブレーキ用のアダプターも売っている。(取扱説明書は添付されていない。)
・BALL BEARING 7 ROAD
他に何かいい手はないかと色々調べた結果、ロード用のディスクブレーキがあることを突き止めた。AVIDという米国メーカーの『BB7 ROAD』(定価:11,329円)という製品だ。これならロード用STIで何の問題もなくディスクブレーキを使うことができる。しかもスマート!(日本製に比べるとやはり仕上げが雑だけどね。)

【拡】日本での販売価格は1万円前後(1ヶ)。ちょっと重いけどキレイにまとまります。
AVIDはSRAMの傘下に入ったんだね。
・シマノ BR-R505
2007年にシマノからもロード用のディスクブレーキが発売された。型番からわかるようにデオーレより下位グレードのようで、重量がフロント:218g、リア:223gもある。ディスクブレーキは元々重いので、もう少し軽量のモデルもリリースして欲しい。(が、需要はあまりないと思うので無理だろう。)

ロードバイク用メカニカルディスクブレーキシステム
BR-R505
メーカー希望小売価格 7,258円 (前または後、キャリパー本体/ローター)
「BALL BEARING 7 ROAD」の重量はメーカーのHPを見ると318gと表示してあったので、シマノのBR-R505の方が断然軽いと思い、BR-R505への換装を考えるが、「BALL BEARING 7 ROAD」を実測してみたら211gだった。どうやら318gという重さはローター込みらしいので、結局重量差はほとんどないようだ。
ディスクブレーキは重量的・価格的に見れば不利だが、リムの振れに影響されないことや雨や泥に対しても制動力が落ちにくいというブレーキ性能の面ではピカイチ。またバイクに装着したときの存在感とカッコよさはVブレーキなどの比ではない。とはいっても、ディスクブレーキはリムブレーキとブレーキの効きのフィーリングが違うので、同じ感覚でブレーキングすると前輪ロックで前転する恐れがあるので気を付けたい。
ほかにロード用ブレーキレバーでブレーキ本体を操る方法として次のような組み合わせが考えられる。『ダイアコンペ 287V』(定価5,554円)はレバー比をVブレーキに合わせたロード用ブレーキレバーであるが、同製品を用いた場合は当然のことながらギア変速をバーコンやWレバー等に頼ることになる。私としてはSTIでギア変速できるシステムをオススメしたいところだ。

シマノ STIレバー |
|

ダイアコンペ 287V |
| ブレーキ本体 | STI | 287V |
| カンチブレーキ | ○ | × |
| Vブレーキ | × | ◎ |
| Vブレーキ+TravelAgent | ○ | × |
| ミニVブレーキ | △ | △ |
| メカニカル・ディスクブレーキ | × | ◎ |
メカニカル・ディスクブレーキ
+TravelAgent(In-Line) | ○ | × |
AVID BALL BEARING ROAD
(ロード用メカニカルディスクブレーキ) | ◎ | × |
シマノ BR-R505
(ロード用メカニカルディスクブレーキ) | ◎ | × |
カンチブレーキが一番安上がりで気軽だが、ストッピングパワーはディスクやVブレーキに比べ格段に落ちる。(雨の日の下り坂などではまったく止まらない!)なので無理に効かせようとするとブレーキレバーを強く引くことになり、結果ワイヤーに大きな力が加えられるので消耗が早くなってしまう。ちなみに、自分はいままでカンチのブレーキワイヤーを2回ブッち切ったことがある。元々カンチはオフロードバイク仕様のブレーキだし、オンロードを高速で走る用途には向かないといえよう。
□サドル廻り
サドルは安物だとすぐ尻が痛くなってしまうので、ここは特にケチらず実績のあるメーカーの製品をチョイスするのが正しい。で、サンマルコの『2004 ERA K Ti 』を購入。レーシーなデザインで速そうな感じがする。シートピラーはニューULTEGRA。サイズさえ合えばMTBにロード用ピラーでもまったく問題ない。

05年より04年モデルのデザインの方がカッコイイ。
シートピンは盗難に遭わないようクイック式からアーレンキータイプに換装。また、キャットアイのフラッシングライトは雨にあまり強くないのでサドルが屋根代わりになるようセットした。

目立たずクール。
□スプロケット
フロントハブはロード、MTBともエンド幅が100mmなので相互利用可能なのだが、リアはロード130mmに対してMTBは135mmなので互換が効かない。ただし、スプロケットの規格はまったく同じなので、ディレイラーのキャパシティが許容する限りMTB用のデオーレLXにULTEGRAのカセットスプロケットを装着することは可能だ。

変速性能はすこぶるスムーズ。
□特別工作
サスペンションフォークをリジッドに換装するとどうしても肩下とタイヤとの間がスカスカしてしまい、細いタイヤだとなおさらスカスカ感が強調される。これはどう見てもスマートではないのでこの空間を有効利用すべく、実用の観点からライトの設置を決めた。ライトはコンパクトで電池の確保が容易な単三仕様のキャットアイ「HL-EL120」をチョイス。上手い具合にフォークにはネジが通せる穴があいているのでこれを使って取り付けた。
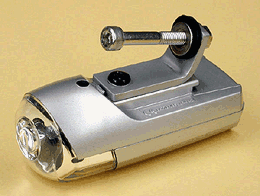

フレームカラーに合わせてシルバーを購入。
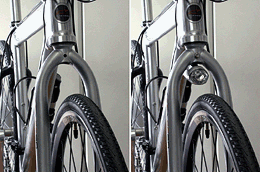
【拡】左がライト設置前。右が設置後。
取り付けネジはホームセンターで購入。見た目を考えてアーレンキーネジ。アルミの板を曲げ穴を開けてネジを通して取り付けただけの簡単な工作だが、スカスカ感を実用的なライト設置でスマートに解決! この取り付け方だとスイッチ操作も電池交換も容易な上、盗難にも遭いにくい。
フレームカラーだが、メーカーが用意していたレーシングカラーもそんなに悪くはないのだが大量生産製品故に無個性であり、チネリやコルナゴといったブランド的なステータスもない「ANCHOR」のロゴがイマイチ気に入らなかったこともあってロゴ無しをオーダーした。しかし現物を目の当たりにするとマーキングがまったくないフレームは締まりがないので市販の『Bridgestoneステッカー』でステッカーチューンを施すことを考える。
【拡】シンプル好きな私ではあるが、単色塗装のみだと寂しすぎる…

(大)サイズはカーショップのWeb通販で購入するが…
なんとかネット通販でブリヂストンのステッカーを入手。30cmほどのものを探すも、こういうスモールパーツはなかなか見つけ出すのは難しい。それにしてもタキ○ワで購入したステッカー(小)は質が悪すぎ。最悪。率直に言って「なんだよこれーっ!?」って感じ。(とても耐えられる出来じゃなかったので結局使わずに捨てちゃったよ…)これってメーカー公認じゃないですよね…?
□オリジナルマーキングに作戦変更
市販のステッカーチューンではあまりスマートな仕上がりは期待できそうもないので思い切って完全自作のオリジナルマーキングに変更することを決意。マーキングは初めてのことなので機材や素材、技法等々で試行錯誤しホントに色々苦労したが、なんとかカッコのついた出来映えになったと思う。オリジナルのマーキングは色やサイズを自由にできデザイン的に断然有利な上、市販ステッカーやカッティングシートでは難しい厚みの段差をなくす処理も施したのでムチャクチャクール! シマノさえも凌駕したサンツアー「SUPERBE PRO」のまったく凹凸のない美しいマーキングのよう。 自転車に相当詳しい人でもない限りメーカー純正といっても通用するクオリティだ。

【拡】完全オリジナルのシンプルなアンカーフレームデザイン

コロンブスのチューブを使ったアンカーフレーム!?

【拡】EASTONのMTB用クロモリフォーク!? 白文字もOK!


DURA-ACEの補助ブレーキレバーとプレッシャープラグ!?
クリアコーティングの処理を施しているので光沢があり、ちょっとやそっとのことじゃ禿げません。(但し、やっぱりメーカーの焼付塗装に比べると耐久性で落ちる。)こういうインチキマーキングを施すのは楽しい。パソコンの普及で高度な工作ができるようになった。
□総 評
何だかんだでほとんどのパーツを換装するハメになり予想以上に費用がかかった。なんか初めからフレーム単体で買えばよかったと若干後悔…。(ここまで本気で組むつもりはなかったので。)それはともかく、デフォルトのMTB仕様は安物パーツで構成されていてチープ感が漂っていたが、スタイル的・パーツ的・マーキングデザイン的にもスマートかつ個性的で満足のいくドロップハンドル仕様MTBに大変身した。我ながら満足できる出来映えである。もう見た目はMTBではなくレーサーですね。


【拡】デフォルトのMTB仕様と換装仕様の比較。スタイルはもちろん、質感が全然違います。
本当はショップで組んでもらうつもりだったのだが、近所に頼れるだけの知識を持ったショップがなかったのでやむなく自分で調べて組み立てた。ちょっと相談しても簡単に「無理」とか「保証できない」とか、明らかに事実と異なるウソの説明をしたりして全然信用できなかった。コイルスプリングを使ったサスがどうすりゃエア抜けするんだよ! 結局、色々な知識や技法を得ることができたので自分で組み立てることになって正解だったけど。(笑
重量は12.8kg→10.4kgと大幅に減量できた。ロード用の軽量パーツへの換装とともにフロントフォークと車輪の重量軽減が大きい。ただ、まだロードと比べるとかなり重いのでさらなる軽量化を図るつもりである。
デフォルトのMTBではポジション的にロード乗りに追いすがることができなかったが、換装後はロードレーサーと互角に近い走りができるようになった。(ヘタレなロードは相手じゃない。とはいえ、ホントに速いロードには敵いません。ロードレーサーと比べると高速巡航時では4%ほど遅い。)また、雨天走行ではロードとは比較にならないほど安定した走りを実現。普段の足としてはロードとMTBのいいとこ取り的なバイクで、思っていた以上に重宝している。
【拡】クールで満足できる出来映え。MTBドロップハンドル化計画大成功!
更なる軽量化を実施。
→第二次換装軽量化計画
|
|
